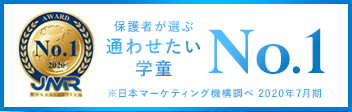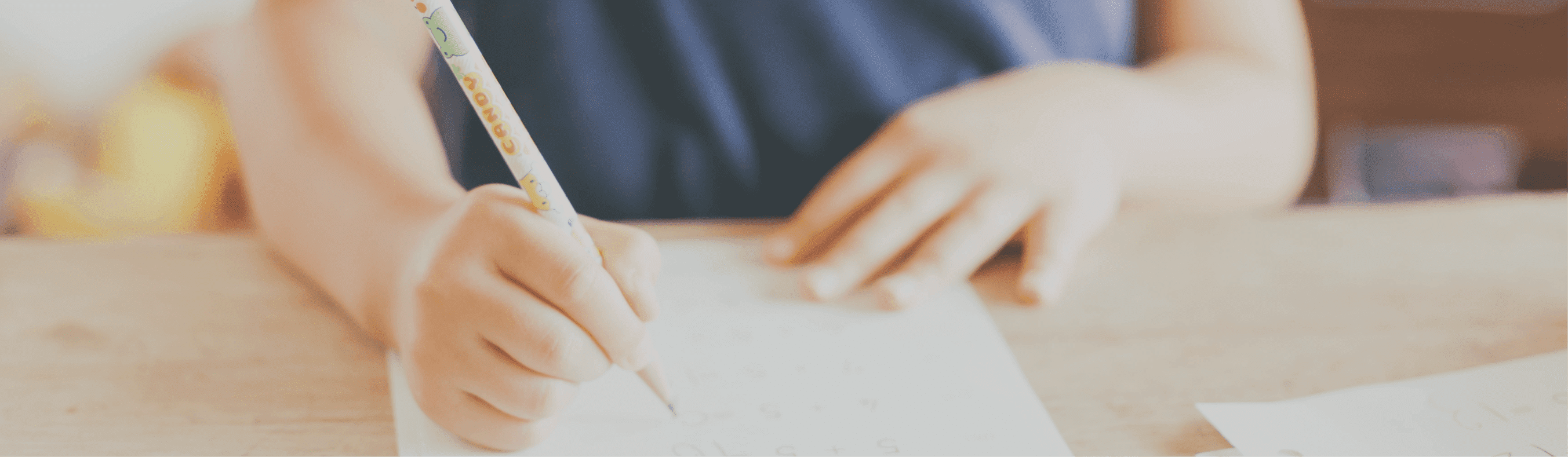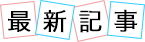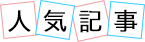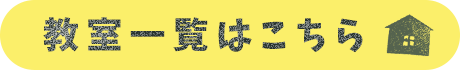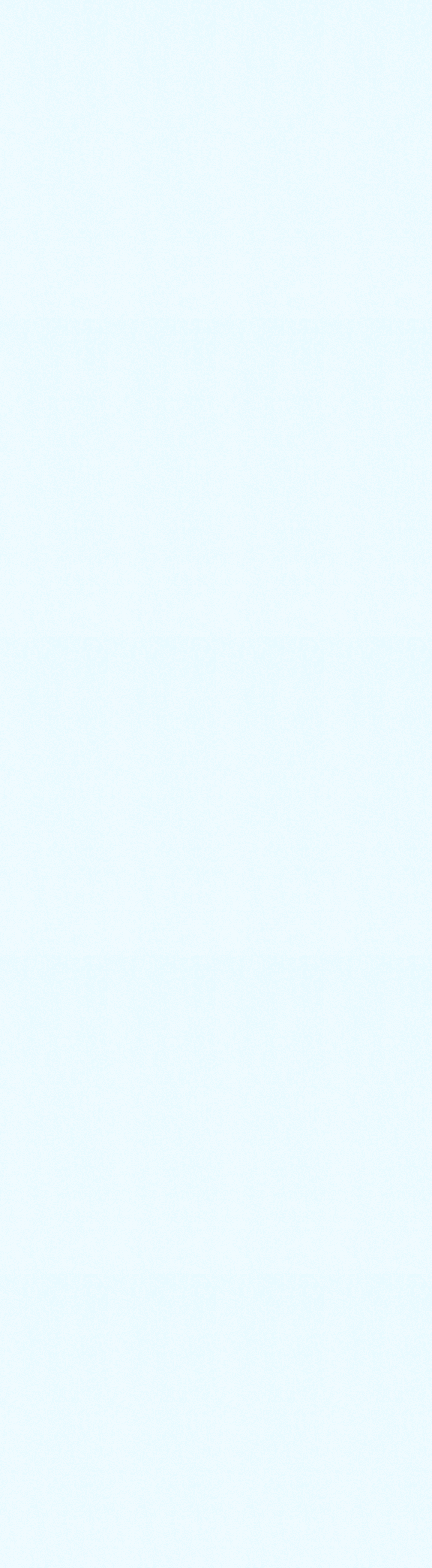
お年玉いくらあげたらいいの?年齢別の相場を紹介します。
最終更新日:2020/03/29
お年玉はいくらあげたらいいの?
年末年始、家族や親戚で集まる機会が多くなるのではないでしょうか。ハレの日や年中行事、日本の伝統を子どもに伝えられる、とても良い時期です。また、子どもにとっても、ママやパパにとっても、普段と違う場や人たちと過ごす時間はかけがえのない時間なのではないでしょうか。
しかし、子どもの頭の中でグルグル回っているのは「お年玉」のこと。いくらもらえるかな、何に使おうかなとワクワクしている子どもに対して、いくら渡したらいいのか、兄弟姉妹がいるから金額に差をつけたほうがいいのか、まだ自分ではお金を使える年齢ではないからどう管理しようかなど、ママやパパの頭の中は悩みでいっぱいかもしれません。
そこで今回は、年齢別のお年玉の相場と、お年玉を渡すときに気をつけておきたいこと、その使い道などをお伝えしていきたいと思います。

未就園児・未就学児のお年玉の相場
0歳から3歳までは、まだお金の概念を理解することが難しい時期です。そのため、お年玉として特別にお金を渡すよりは、簡単なおもちゃやベビーグッズを手渡すほうが無難かもしれません。お年玉をお金ではなくプレゼントとして渡す方法です。
プレゼントの場合は、予算が500円から1,000円程度が相場といわれています。未就園児の年頃では、安い・高いといった金額的な基準ではなく、渡したこと自体に価値があるのです。
保育園や幼稚園に通うようになったら、お店屋さんごっこなどで遊ぶようになり、お金という概念を少しずつ理解するようになります。ママ・パパと買い物に行って、レジでお金を支払ったり、お釣りをもらったりする姿に興味を持つこともあるのではないでしょうか。
そのため、お年玉はお金で渡してあげるとよいでしょう。金額は1,000円から2,000円程度が相場といわれています。同じ1,000円でも500円玉2枚といった硬貨で渡し、重量感を伝えるのもアイデアです。
小学校低学年のお年玉の相場
小学校低学年の子どもへのお年玉の相場は1,000円から3,000円程度といわれています。
小学校に入学すると、行動範囲が少し広がり、友だちと遊ぶことも増えていきます。小学校低学年のうちは、お金を使って遊ぶことは少なく、友だちのおうちに行き来したり、公園で遊んだりすることが多いのではないでしょうか。
また、買い物をするときにも、ママやパパと一緒に行くため、自分の欲しいものを自分で買うという機会はそこまで多くはないでしょう。そのため、未就学児より少し金額を上げて渡すという傾向が強いようです。
小学校高学年のお年玉の相場
小学校高学年になると、お年玉の相場は3,000円から5,000円程度になります。
この年頃になれば、行動範囲もぐんと広がり、子どもたちだけで遠くに遊びに行くようにもなります。また、1人で買い物をするということにも抵抗感がなくなるようになります。
ある程度、自分のお金を自分で管理することもできるようになり、好きなものを買ったり、お金を貯めたりする考え方の基礎も身についてきています。そのため、お年玉の相場も、子どもたちが遊んだり、欲しいものを買ったりする際の、ちょっとした上積みにできる金額になるのです。
お年玉を渡すときに気をつけたいこと
ここまでは、お年玉を渡すときの年齢別の相場についてお伝えしました。これからは、お年玉を渡すときに気を付けたいことをお伝えします。実は、お年玉を渡すときには、金額以外にも気にかけておきたいことがあるのです。
おじいちゃん・おばあちゃんとの金額調整
子どもにお年玉をあげるのは、ママやパパだけではない場合も多いです。1番もらう機会が多いのは、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんからではないでしょうか。
その時にも気をつけたいのが、お年玉の金額。例えば、両家の間でお年玉の金額に大きな差があると、気の遣い合いになってしまうことが考えられます。
また、子どもは正直なので、無用なトラブルなつながってしまう事もあるかもしれません。そのため、ママやパパが、最初からそれぞれのおじいちゃんおばあちゃんと金額を調整しておく事で、問題が取り越し苦労で終わるかもしれません。
あげすぎないことも大切
子どもにとって、自分で自由に使うことのできるお金というのはとても貴重なものです。そのため、普段のお小遣いが少なかったり、お手伝いの対価としてお金をもらったりしていると「年に一度のことだし…」と思い、相場よりも多めに渡しているお家もあるのではないでしょうか。
しかし、あげ過ぎることも考えものです。まだ十分に金銭感覚が備っていない子どもは、大金をもらってもうまく活用できず、お年玉が悲しい思い出になってしまうかもしれません。お年玉は金額よりも「気持ち」が大切ですから、トラブルのタネになりそうなことは避けるようにすることも考えてみてください。
もらったお年玉はどうすればいい?
最後に、もらったお年玉のおすすめの使いみちをお伝えします。
子どもにとってお年玉はふだんの生活ではあまり触れることのない大きなお金。お金の教育をするのにも最適な機会です。ママもパパも子どもも納得するような方法の例をお伝えさせていただきます。
「使う」
最初は「使う」という視点です。
子どもの欲しいものややりたいことにお金を使うことで、欲しかったものが手に入ったという喜びを感じることができます。
また、子どもが自分の頭で何を買うかということを考えることで、自主性を伸ばす機会になります。単に浪費した・消費したという使い方に留まらず、子どもにとって、いい買い物ができたと思える使い方を探してあげたいですね。
さらに「何を買うか」「どこで買うか」「どうやって買うか」などをママやパパと一緒に調べたり実際に買いに行ったりすることで、モノの流れや経済に触れるきっかけにもなります。「あのお店とこのお店では値段が違うんだね、どうしてだろう?」といった会話が親子でできると、生活に根ざした学びをすることにつながります。
「貯める」
次は「貯める」という視点です。
お年玉を貯金するというのは多くの家庭で行っていることですが、「何のために貯金をするのか」ということを明確にすることで子どもの経済感覚や目標を決めて努力する機会につながります。
ふだんからお小遣いを渡しているお家だと、お年玉とお小遣いを合わせて大きな買い物をすることもできます。また、今は欲しいものがないという子どもでも、将来のためにただ貯めるという理由だけではなく、親子で納得する理由を見つけて貯金をしてあげてください。その際に、一緒に銀行に行ってATMを操作させてあげると、子ども自身が自分のお金を自分で預けるという貴重な体験もできる機会になるでしょう。
「増やす」
最後は「増やす」という視点です。
ただ、今回は体験を増やすという意味の「増やす」ということです。投資など実際にお金を増やす体験ではありません。
さまざまなイベントやワークショップ、習い事の体験教室などといった、お年玉の金額で行える体験を増やす機会は多くあります。ママやパパが子どもの興味関心に寄り添った選択肢を何種類が作って、子どもに選んでもらい、選んだものを実際に体験させてあげるという機会を作ってあげるのはいかがでしょうか?
子どもが自分で選ぶことで、積極性や自主性を伸ばす機会になりますし、子ども自身も自分のお金を使って体験をするということで、やる気を持って体験することができるでしょう。習い事につながる可能性もありますし、親子での素敵な思い出にもなります。

まとめ
今回は、年齢別でのお年玉の相場や気を付けたいこと、お年玉の活用方法などをご紹介させていただきました。お年玉は渡す方ももらう方も考えることがたくさんあり、ママやパパは大変かもしれませんが、子どもにとっては純粋に楽しみな体験の一つです。
ただ、忘れてはならないのは、どんな使い方をするとしても子どもが納得し、「○○してよかった」と思えることです。子どもに我慢をさせてしまったり、楽しくない思い出になってしまったりすることがないように、親子で一緒になっていろいろな使い方を考えて見ましょう。