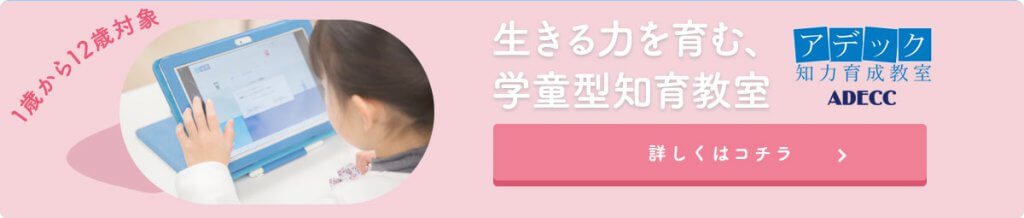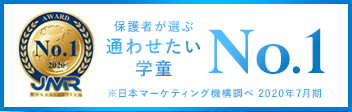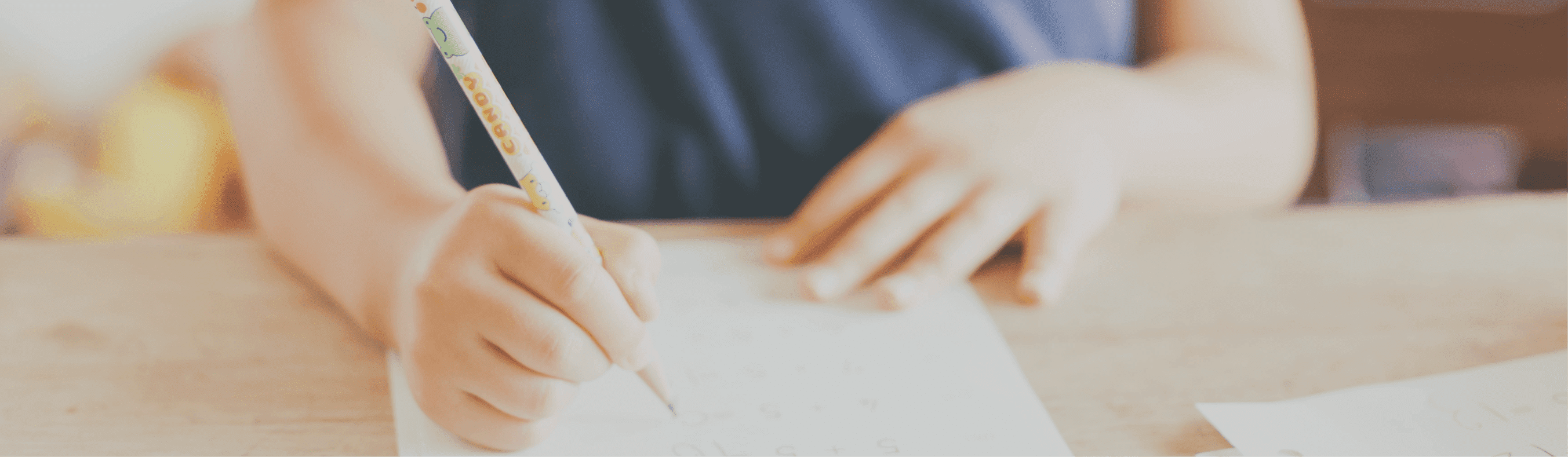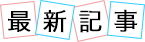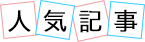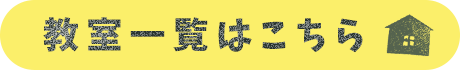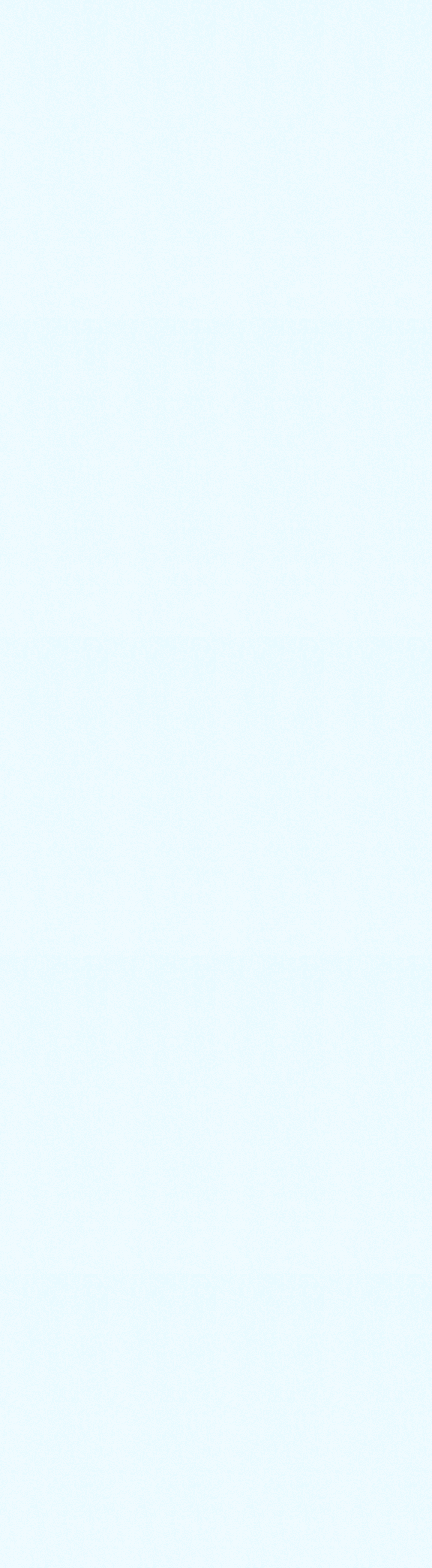
デジタルゲームは子どもにとって悪影響か?ゲームとのうまい付き合い方とは
最終更新日:2021/07/11
デジタルゲームは子どもにとって善か?悪か?
テレビゲームが出てきたときから、つまりデジタルゲームの誕生したときから、「ゲームは子どもにとって悪影響だ」、「ゲームをすると子どもがバカになる」などという議論はずっとありますね。他にも「暴力的なゲームをすると、子どもの暴力性が増す」なんて話もありますね。
テレビゲームだけでなく、ポータブルゲームも充実し、最近ではスマホゲームも出てきて、デジタルゲームはいつでも、どこでもできるようになってしまいました。誰も止めなければ、子どもは飽きるまでずっとゲームをしてしまうでしょう。
しかし、これは本当に悪影響なのでしょうか。子ども時代に何かに熱中することは、脳を刺激し脳の発達を助けると前にも述べましたし、きっと悪いことばかりではないのではないでしょうか。
今回はデジタルゲームのメリット、デメリットを整理して、結局子どもにとって悪影響なのかどうかはっきりしましょう。

デジタルゲームのメリットとデメリット
ここからはデジタルゲームのメリット、デメリットについてお伝えしていきます。
デジタルゲームのメリット
まずは、テレビゲームやスマホゲームをするメリットについてお伝えしていきます。デジタルゲームをすると、子どもの脳機能に間違いなく良い影響があります。
例えば、注意力をキープし続ける能力が上がること、複数ある情報の中から特定のものに注意を向ける能力、つまりは集中力が上がると言えます。
また、脳の中の記憶と学習を司る分野である海馬が大きくなるとも言われており、記憶力も上がります。
集中力と記憶力、この2つは勉強をするにあたって、嬉しいメリットではないでしょうか。
デジタルゲームのデメリット
次に、デジタルゲームするデメリットについてお伝えしていきます。
子どもは、ママ、パパに「良い加減にゲームやめなさい!」と言われるまで、ずっとゲームをしていますよね。これはもしかしたら子どもが「ゲーム中毒状態」になっているからかもしれません。
ほとんどのゲームは一定の間隔でアイテムがもらえたり、ステージをクリアできたりと、報酬を得ることができます。このときに脳の報酬系というところから、ドーパミンが放出されます。すると、「気持ち良い!」という快感が得られ、その快感の原因となったゲームを「もっとしたい!」となり、次の報酬をもらい、また快感を得ます。これの繰り返しで、報酬系はオーバーヒートを起こしやすくなるんですね。さらに、最近のゲームは良くできていて、報酬をうまいタイミングで与えてきます。
結果、デジタルゲームをすると、目の前の報酬に弱くなり、自己コントロールがしにくくなってしまうのです。また、そうなってしまうと、ゲームをしていなければ、イライラしてしまうなんてということもなりかねません。
結果、デジタルゲームは善なのか、悪なのか
デジタルゲームのメリット、デメリットをそれぞれお伝えしてきました。
たしかにゲームは学力アップに役立つ脳機能を高めてくれます。しかし、報酬に弱くさせて、自己コントロール能力を低下させますから、勉強というコツコツと努力しなければならないものができにくくなってしまいます。つまり、せっかく向上した脳機能を活かすことができないということになります。
また、近年の研究では、人生の成功(年収や仕事への満足度の高さ、学歴の高さ、犯罪率の低さ、肥満率の低さ、長生きできるかどうかなど)は、脳機能の高さよりも、自己コントロールや努力できることが重要と言われています。
デジタルゲームは豊かな人生を送るために必要な能力を、子どもから奪ってしまう可能性があり、悪影響であると言うことができるかもしれません。

デジタルゲームとのうまい付き合い方
デジタルゲームがいくら悪影響だからと言っても、まったく与えなかったり、取り上げてしまうのは、あまり現実的な方法ではないでしょう。
家にゲームがないから安心と言うわけではなく、友だちの家に行けば大抵あるでしょうし、自分のお金で自由に使えるようになったときに買うこともできます。そのときに抑えられた分だけ、気持ちが爆発するということになりかねません。
また、先ほどのゲームによって自己コントロールできなくなる話は、子どもだけでなく、大人にでも十分当てはまります。子どものうちからデジタルゲームとのうまい付き合い方を覚えておくといいでしょう。
ここからは、デジタルゲームのうまい付き合い方といくつかご紹介していきます。
デジタルゲームをする時間やタイミング
まずは、「デジタルゲームをする時間やタイミング」です。
先ほど述べたとおり、最近のデジタルゲームは飽きづらく設計されているので、ゲームをする時間を子どもの判断に任せてしまうと、延々とプレイし続け、ゲーム中毒状態になる可能性があるでしょう。子どものゲームする時間を制限しましょう。
例えば、「ゲームは1日2時間まで」など使用時間を制限したり、「夕食後は30分」などしてもいいタイミングを制限したりです。
特に制限したいのが、寝る前の数時間前です。テレビやスマホの画面の光を浴びずにいることで、眠りに自然と就くことができます。そのため、生活のリズムも整います。
ゲーム時間をご褒美に使う
次に、「ゲーム時間をご褒美に使う」です。
例えば、「勉強を1時間できたら、ご褒美にゲームを30分やってもいい」、「宿題をやったらゲームをしてもいい」などという条件を設定しましょう。ただ「〇〇時間までしかゲームをやってはいけない」というよりも、勉強をしなければならない条件を達成するまで我慢しないといけないので、自己コントロールを高めることにもなります。
また、勉強を頑張ったからこそ、達成感や満足感を得られ、このときも、ドーパミンが放出されます。そして、勉強後のゲームによって放出されるドーパミン。二重で得られる快感によって、「勉強=楽しいもの」と脳が錯覚してくれるかもしれません。
他のものに熱中させる
次に、「他のものに熱中させる」です。
子どもがデジタルゲームへの熱が抑えられないならば、ほかのことに熱中させ、ゲームから興味をなくさせてみようと試みるのも、1つの手段です。例えば、子どもがゲームよりも夢中になりそうな習い事をさせて、ゲームのことを忘れさせてみましょう。
ゲームでは比較的、刺激から刺激への間隔が短く、ドーパミンを感じにくくなりやすいです。ドーパミンがなくなると、ものごとへのやる気がなくなってしまいます。
習い事では、ゲームのように簡単には刺激を得ることはできません。そのため、刺激と刺激の間隔が長く、ドーパミンが感じやすく、やる気も挑戦心も高まるでしょう。
家族でアナログゲームをしよう
子どもたちにとって「デジタルゲームは面白い。ボードゲームなどのアナログなものは、つまらない」というイメージがあるかもしれません。しかし、そんなことはありません。最近ではアナログゲームも進化し、トランプやオセロだけでなく、楽しいものばかりです。
また、ママ、パパにとって嬉しいのは、アナログゲーム遊ぶうちに子どもの言語能力が伸びるという点です。これはテレビゲームやスマホゲームよりも、プレイヤーと面と向かって遊ぶ分、相手とのコミュニケーションの量や、相手の表情から手の内を読む量が圧倒的に多くなるからではないでしょうか。
ママやパパは子どものプレイの仕方を見て、子どもの性格や考え方に気づくことができます。逆に、子どももママ、パパの性格や考え方に気づくことができます。普段のコミュニケーションだけでは、知り得ないことも知ることができるでしょう。

まとめ
いかがだったでしょうか。デジタルゲームの子どもへの影響についてお伝えしてきました。
デジタルゲームは悪影響であるというのが私の見解ですが、子どもにデジタルゲームを完全に禁止することはできませんし、しないほうが、ゲームとのうまい付き合い方を覚えていくでしょう。
ちなみに、冒頭で述べた「暴力的なゲームをすると、子どもの暴力性が増す」というのは、たしかにある話なのですが、暴力的なゲームの影響はほんのわずかだそうです。