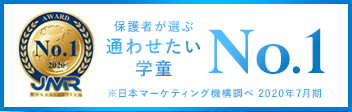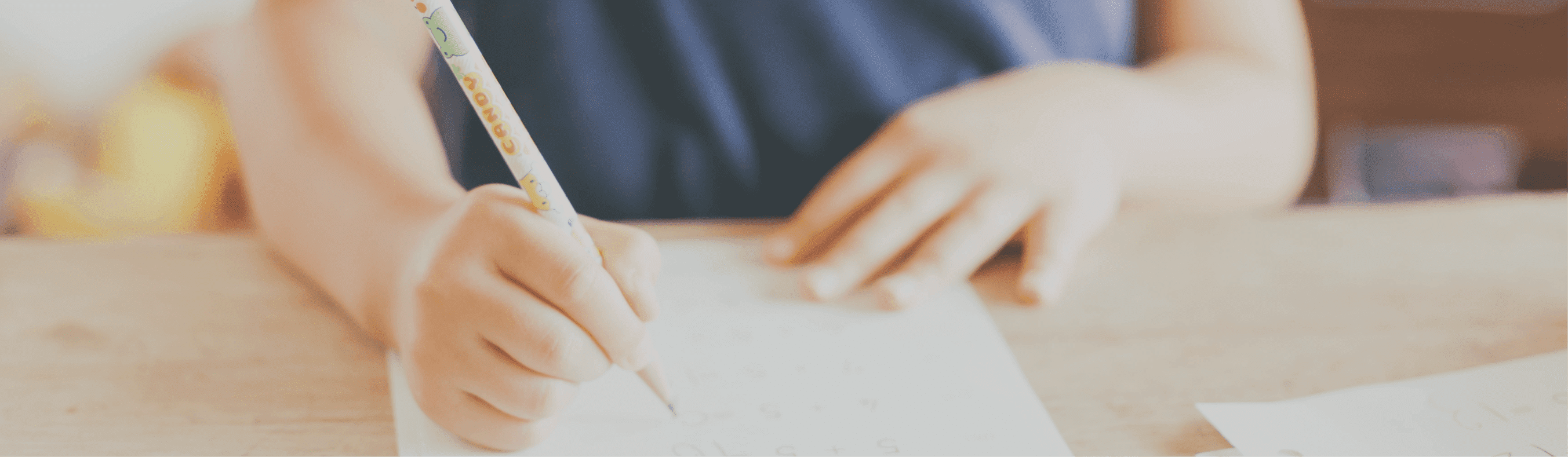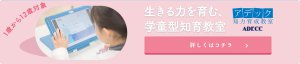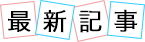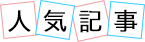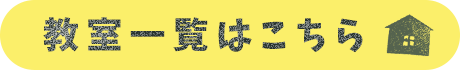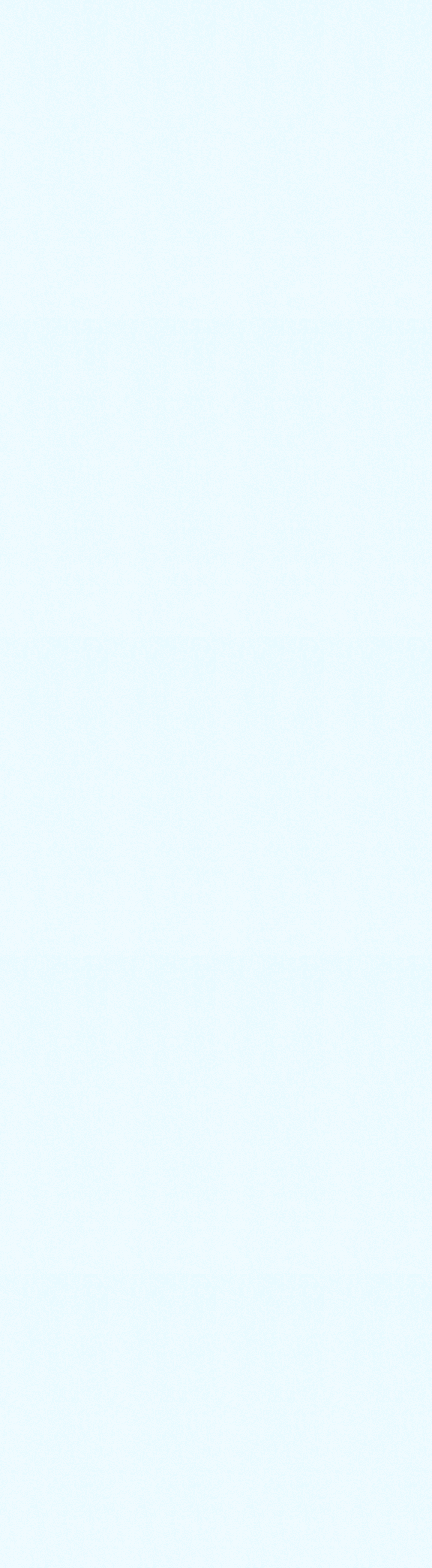
奥深さと親しみやすさいっぱいの「わらべうた」を、子どもと一緒に楽しもう
最終更新日:2023/03/11
子どもが楽しめる音楽ときいて、真っ先に思い浮かぶものといえば「わらべうた」。小さな頃にわらべうたを歌ったり、わらべうたで遊んだ経験をもつパパやママも多いのでは?
私たちにとっても身近な「わらべうた」ですが、単に「子どもが親しみやすい音楽」というだけでなく、言葉と音楽、動きと遊びが一体になったものとして、子どもの心身の成長・発達への効果が注目されているそうなんです。
今回は、「全国わらべうた&コダーネットワーク事務局」の本澤陽一さんに、わらべうたの魅力や子どもへの教育効果、親子で楽しめるおすすめの遊び方についてお話を伺いました。
◆わらべうたと童謡の違いとは?
まず本澤さんに伺ったのは「わらべうた」とはそもそも何か、ということ。実は「わらべうた」と「童謡」は別のものなのだと本澤さんは言います。
「『わらべうた』と『童謡』はよく似ていますが、一番の違いは、作者の存在です。童謡は、作詞・作曲した人がいて、大人が子どものために作った歌です。一方、わらべうたは古くから歌い継がれてきた歌で、いつ、誰によって作られたのかはわかりません。平安時代や、もしかするともっともっと昔からあったものかもしれないのです」
長い時間をかけて歌い継がれてきた「わらべうた」。いま歌われているわらべうたも、時代の流れに沿って歌詞や節回しが少しずつ変化してきているのではないか、と本澤さんは言います。わらべうたの背景には、歴史や人々の暮らしや思いが根付いているのだと考えると、「親しみやすい」という以上の奥深さが感じられますね。
また、「伴奏がない」ということもわらべうたの特徴のひとつなんだそう。幼児番組などで、わらべうたを歌う場合は、伴奏がつけられていることも多いのですが、もともとは子どもたちが遊びながら歌う歌なので、伴奏がなく、「ことば」と「音程」のみの歌なのです。
「歌に伴奏がプラスされると、赤ちゃんや幼児にとっては情報過多になることもあります。伴奏のないわらべうただからこそ、お母さんの肉声や愛情がストレートに伝わるんですよ」
また、明確な作者がないわらべうたには、正式な題名がないという特徴も。そのため、歌の出だしの言葉が題名として浸透しているのだそうです。
◆わたしたちの身近には、こんなわらべうたが
たとえば、『だるまさんがころんだ』『かごめかごめ』『通りゃんせ』『あんたがたどこさ』『げんこつやまのたぬきさん』『ねんねこしゃっしゃりませ』などは、一見童謡のようですが、わらべうたです。さらに、本澤さんによるとお母さんが赤ちゃんをあやすときの声がけの「いないないばあ」も、実はごく短いわらべうたの一種なのだそう。
「わらべうたには子どもたちが自身が遊びながら歌う『遊び歌』の他に、『いないないばあ』のようにお母さんが赤ちゃんや幼児に語りかける『遊ばせ歌』もあります。また、はっきりとした音程のない『唱え歌』や、土地に根づいた民謡の要素もプラスされた『子守歌』などもあります」。
「いないいないばあ」が、赤ちゃんをあやす言葉でもあり、わらべうただったなんて、感慨深いものがありますよね。
「長く歌い継がれてきた歴史のなかで、消えてしまったわらべうたもたくさんあると思います。だからこそ、今残っているわらべうたは、音程もわかりやすく、子どもの耳に残りやすいものだとも言えます。海岸や水辺に行くと、波や水に何年も何年ももまれ続けて丸くなった石があるでしょう。角もギザギザもない石は私たちの手になじみ、その形からはやさしさや安らぎが伝わってくるような気がしませんか?わらべうたとはそういうものではないかと私は思っているんです」
◆わらべうたは、愛情を伝えるツール
それでは、わらべうたを歌い聞かせることは、子どもにとってどのようなメリットがあるのでしょう。本澤さんは、わらべうたは「母の愛情を伝えるツール」だと言います。
「赤ちゃんや幼児をあやすとき、お母さんは抱っこをしたり、話しかけたり、歌いかけたりしますよね。わらべうたには、そうしたすべてのツールが含まれているのです。さらにわらべうたには伴奏もなく、長い歴史のなかで、余分なものが削られていって今に伝わる純粋な歌。だからこそ、シンプルかつまっすぐに子どもの心に届くものだと言えます」
大人になると、わらべうたを聴いたり歌ったりする機会は減ります。でもわが子が生まれると、子どもをあやしながら自然にわらべうたを口ずさむ方も多いのではないでしょうか。それはかつて自分が小さい頃、お母さんやおばあちゃんのわらべうたを聴いて育ったからなのかも。一度は歌わなくなっても、私たちの心のどこかにわらべうたは根づいているのですね。
本澤さんが、わらべうたの魅力や尊さを認識したのは、こんな奇跡のような出来事があったからだと言います。
「養護施設で働いていたときは、重度の障がいを持つ子どもたちと過ごしていました。話しかけても身体を揺すっても、抱っこしてもあやしても表情ひとつ動きません。そんなある日、障がいを持つ子どもを抱っこしながらわらべうたを歌ってみたんです。すると、その子の表情がふと和らいだんです。驚き、とても感動しました。解明はできないけれど、わらべうたには、子どもの心に浸透し、心を動かせる不思議な力があるのではないか、と思ったんです」
◆子どもと一緒にわらべうたを楽しんでみよう!
それでは子どもと一緒にわらべうたを楽しむときは、どんなことに気をつけたらよいのでしょう。
「あまり堅苦しく考える必要はありません。ただし、音程があるわらべうたなら、従来の音程を大切に、最後まで歌ってあげることが大切です」
わらべうたには長い間伝承されてきた「音程」ならではの良さがあります。その音程を崩さず、最後まで聴かせてあげることで、子どもの耳や心に、ストレートに届くのだそうです。
「伝承されてきた歌は、ある意味芸術作品と言っても過言ではありません。ひとつのわらべうたの曲としての完成度はひじょうに高いので、自己流にメロディーを崩すことなく、ぜひ最後まで歌ってあげてください。最初の節を歌うだけで、子どもが喜ぶこともあると思います。親としては子どもが反応してくれると嬉しくて、ついそこで歌を止めてしまったり、子どもが反応する節だけを繰り返してしまうこともあるでしょう。でも、最後まで歌って、その曲全体の流れやその曲の魅力を伝えて欲しいのです」
一方、音程のない「唱え歌」の場合、はっきりとわかりやすく発音することが大切なのだそう。子どもとスキンシップが楽しめる「とうきょうとにほんばし」などはそのひとつ。もともとハッキリとした“ふし”はないので、自然な抑揚をつけながら、一つひとつの言葉をはっきりと発音しながら伝えることが大切。そうすることで、子どもの発語や発音にも良い影響を及ぼすとされています。
◆わらべうたで遊んでみよう!
歌いながら身体を動かしたり、身体の色々な箇所に触れたりといった「遊び」もわらべうたの特徴のひとつ。わらべうた遊びを通じて、体の動かし方や平衡感覚、あるいは「くすぐったい」「痛い」「心地よい」といった皮膚感覚、一緒に遊ぶ相手との距離感や空間認識力といた様々な感覚を育むことも可能です。
また、わらべうたにはわたしたちがあまり意識していなくても、子どもにとって大きな効果を与えるものも少なくないそうです。たとえば『だるまさん』もそのひとつ。
「『だるまさん、だるまさん、にらめっこしましょ』と歌うとき、必ず相手の目を見ますよね。こうすることで、話をするときに相手の目を見ることの大切さや、コミュニケーション力が自然と養われるという説もあります」。
また、小さなときから音程のあるわらべうたをたくさん聴いて育った子どもは、音や旋律を聴く力が身につくことから音程がよく取れ、合唱などの際も上手に歌えるという研究結果もあるのだそう。
このように計り知れない魅力を持つわらべうた。ですが、「わらべうたを子どもたちに歌ってあげてほしいというのは、『音楽的効果があるから』というだけの理由ではありません」と本澤さんは言います。
「わらべうたはずっとずっと伝承されてきたもの。だからこそ、お母さんが聴いて育ったように、愛情を伝えるツールのひとつとして、自分もお子さんに伝えながら親子で楽しんで欲しいな、と思っています」
わらべうたのような、いわゆる伝承されてきた歌は、世界中にありますが、日本の伝承曲(わらべうた)の多さは群を抜いているそうです。何世代にもわたって、歌い継がれてきたわらべうた。あなただけでなく、お父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃん、ひいおじいちゃんやおばあちゃんも同じ歌を聴き、遊んできたのです。
わらべうた=古いうた というイメージを抱きがちですが、わらべうたのことを知れば知るほど、古さよりも伝承のすばらしさ、そして何によりもお母さんの愛情をシンプルに伝えられる歌であることがわかります。
子どもへの愛情を「〇〇ちゃん大好き」という言葉で伝えるだけでなく、わらべうたを通して、音楽や語り掛け、そしてスキンシップを子どもと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。
プロフィール
本澤陽一さん
武蔵野音楽大学作曲科卒業後、約35年間、音楽科の教諭として、小学校、中学校、高等学校、養護学校に勤務。ハンガリーの作曲家・音楽学者・哲学者であるコダーイ・ゾルタンによる自国の伝承音楽をベースとした音楽教育「コダーイメソッド」に感銘を受け、現在は、「全国わらべ歌&コダーイネットワーク事務局」を主宰。日本の伝統のわらべうたの魅力を伝える活動を行っている。