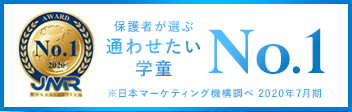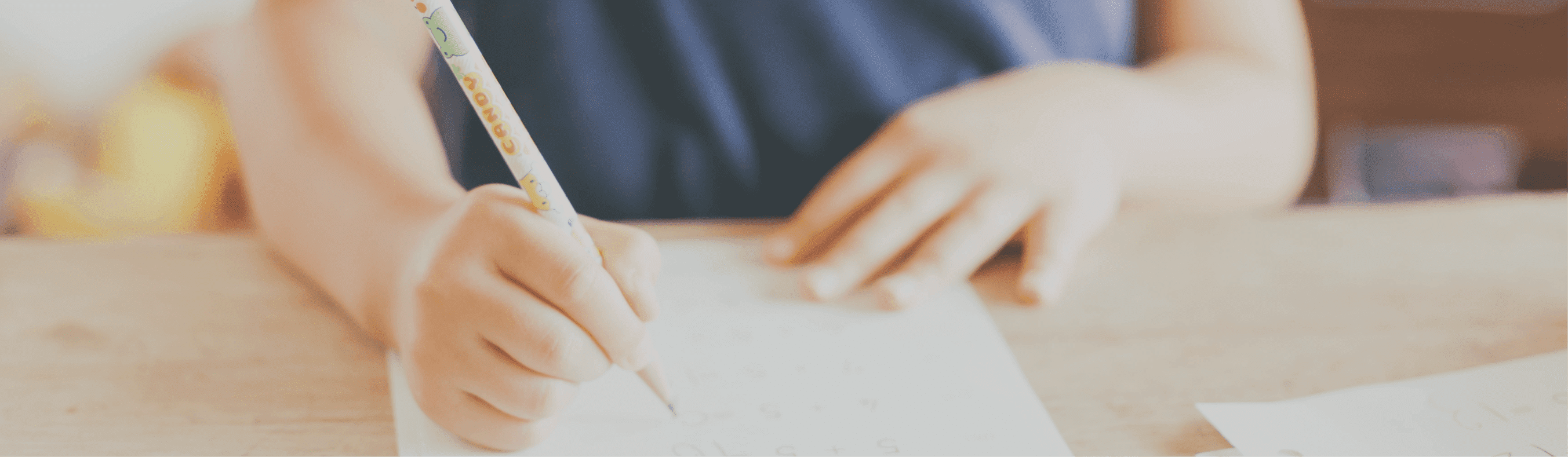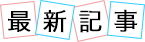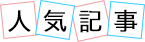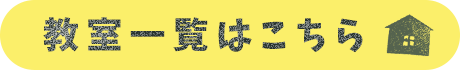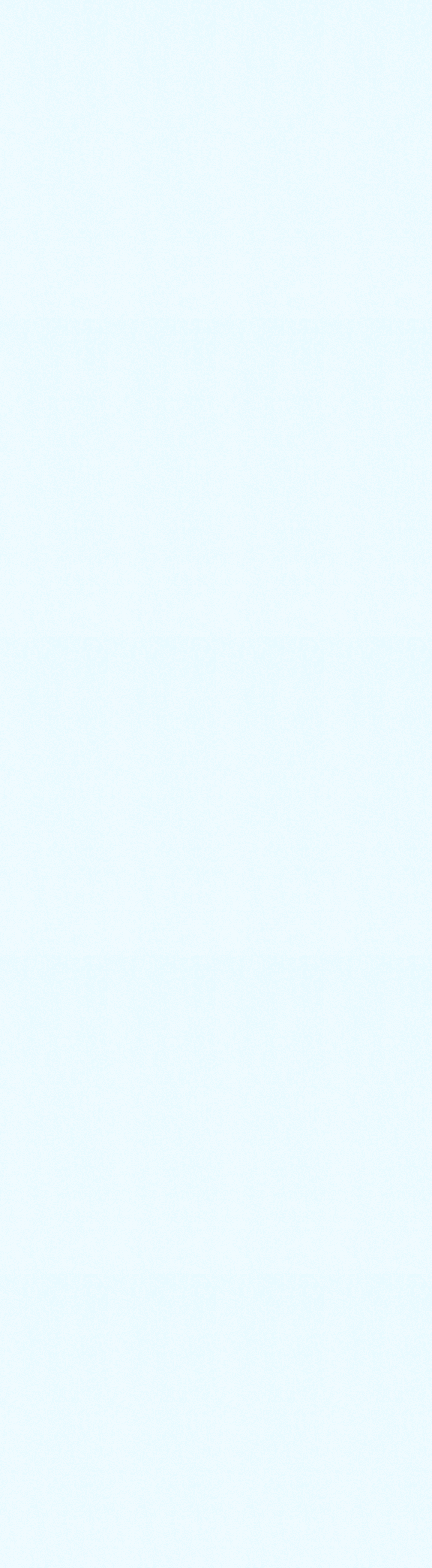
子どもをお勉強好きにしよう!勉強好きな子どもの親にある共通点とは?
最終更新日:2022/01/22
勉強好きな子どもだっている!
勉強が好きな子どもってなかなかいませんよね。私も「勉強しなさい!」と言われないと、机に向かうことができない子どもでした。しかし、子どもの中には「勉強をするのが大好き!」という子もいたりしますよね。
そんな勉強好きな子どもは、どのようにして勉強が好きになるのでしょう。1つに、IQなどが高く、勉強してる内容が理解できるから、勉強が楽しいと感じることが多いからという理由が考えられます。しかし、それだけではないでしょう。
子どもが勉強好きになる大きな理由の1つに、勉強に対する親の関わり方があるはずです。子どもを勉強好きに育てたママ、パパの、子どもへの関わり方を観察したり、話を聞いた人の話によると、そこには共通点があったようです。
今回は、子どもが勉強好きになる親の関わり方をお伝えしていきたいと思います。

子どもを勉強好きに育てる親の勉強への関わり方
さっそくですが、ここからは子どもを勉強好きに育てる親の勉強への関わり方について、ご紹介していきます。
子どもに主体性を持っていると感じさせる
まずは、「子どもに主体性を持っていると感じさせること」です。
子どもが「やらせられている」と感じるのではなく、「自ら勉強をしている」と感じさせるのが、勉強好きの子どものママ、パパはとても上手です。
子どもに自ら勉強していると感じるには、子ども自身に選ばせることです。例えば、親が「この問題からやろう」と選ぶのではなく、子どもに「どの問題からやる?」と選ばせます。また、「どの順番でやる?」、「何時までの目標にする?」などとなにかしら子どもに決めさせることが大事です。
それによって勉強が、「させられている」他人主導のものではなく、「している」自分主導のものと変わります。
ですから、「勉強をしなさい」は勉強好きになるためには禁句です。勉強嫌いの子どもの親の多くは、この言葉を言ってしまいがちです。
「勉強しなさい」と言ってしまうと、自分主導でなくなってしまうことのほかに、「勉強=叱られるもの」というネガティヴなイメージがつきます。人はネガティヴなものを避ける傾向があります。その結果、勉強や宿題をしなくなり、また「勉強をしなさい」と叱られ、負の連鎖が生まれてしまいます。
子どもと一緒に勉強する
次に、「子どもと一緒に勉強すること」です。
勉強好きな子どものママ、パパの中には、子どもと一緒に勉強する方が多いようです。子どもは勉強や宿題をして、親は読書や仕事に関する調べ物をするというような空間が、子どもが勉強するのに適しているそうです。
集中している人がいると、近くにいる人の集中力が上がるというブリュッセル自由大学の研究があります。ママ、パパが集中すれば、子どもも集中できるということです。
また、「勉強=大人がするかっこいいもの」というイメージもつけることができます。ときには、子どもと一緒に計算問題などを解く競争をしてみてもいいかもしれませんね。
「勉強しなさい」は禁句ですが、「一緒に勉強しようよ」は言ってみてもいい言葉でしょう。
子どもが問題を間違えたときの声かけが前向き
次に、「子どもが問題を間違えたときの声かけが前向きであること」です。
勉強好きな子どものママ、パパの声かけは、前向きな言葉であることがとても多いです。
特に、子どもが問題を間違えたとき、普通の親であれば、「そこ間違ってるよ」、「あーもうちょっとだよ」といった声かけをまずしがちです。
しかし、勉強好きな子どものママ、パパは、まず「良く考えたね」、「早く答え出せたね」などと言い、その後に「ここ違ったかもね」、「もう一度解いてみよう」と言います。
要は、初めにポジティブな言葉を言ってあげてから、その後に間違いを指摘します。言われた子どもは、勉強にネガティヴな感じはしませんよね。
これは以前の記事で述べた、親が失敗に対する考え方によって、子どもが「自分の能力や知能はまだまだ伸びる」と信じられるようになるということに関係しているかもしれません。勉強好きな子どもの親は、「失敗は学びのきっかけとなる」という考え方をしていると思われます。
できなかった理由ではなく、できた理由を聞く
次に、「できなかった理由ではなく、できた理由を聞くこと」です。
先ほど述べた通り、勉強好きな子どものママ、パパはポジティブな言葉をかけることが多いです。「なんでこの問題できないの?」なんてことは口にしません。「なんでこの問題できたの?」、「すごいじゃん!」と言って、子どもにできた理由を考えさせます。
そんな親の態度を見れば、子どもは自信をつけることができますし、勉強も楽しくなるはずですよね。
子どもが勉強しているとき、親は笑顔でいる
次に、「子どもが勉強しているとき、親は笑顔でいること」です。
子どもの勉強を見ているとき、勉強好きな子どものママ、パパは、たとえ子どもが理解できなくても、けっして怖い顔をしません。楽しそうに、勉強を教えます。これは、とても重要なことでありながら、難しくもあります。
親の笑顔や温かい態度が、子どもに安心感を与え、勉強に対するイメージをよくします。小さい頃から、これを意識すれば、子どもは勉強を好きになる可能性が高くなります。
×ではなく◯をつける
次に「×ではなく◯をつけること」です。
間違った箇所に×をつけるということを、勉強好きな子どものママ、パパはあまりしないそうです。これもポジティブな声かけをするのと似ていますが、×をつけられるよりも、正解している箇所に◯をつけられてるほうが、子どもの勉強に対するモチベーションは上がりますよね。
さらに、子どもの表情から一生懸命さ、頑張り具合を察して、ここぞというときに、特別な花まるをあげたりするタイミングも、勉強好きな子どものママ、パパは上手だそうです。
答えをすぐには教えない
次に、「答えをすぐには教えないこと」です。
子どもが答えを出そうと一生懸命考えている間は、ヒントや答えなど口を出さずに見守ることも共通点の1つです。子どもが答えを聞いてきたときでも、まずは「どう思う?」などと子どもにさらに考えさせる姿勢でいる大事だそうです。
その結果、自分で考えて答えを導き出し、考える楽しさが子どもに身につきます。考える楽しさがあるから、さらに勉強が楽しいと思えるようです。
子どもの興味を引き出す
次に、「子どもの興味を引き出すこと」です。
子どもに答えを教えるような助けはしませんが、子どもの興味を引き出したり、理解を助けることは、勉強好きな子どものママ、パパはよくします。
例えば、虫について興味を持っていそうなら、昆虫図鑑を買ってあげたり、社会科で地理の勉強をしていたら、地図や地球儀を買ってあげたり、理科で星についての授業をしていたら、星がよく見える場所に連れて行ってあげたりします。勉強と実体験をつなげてあげようという姿勢を、勉強好きな子どものママ、パパは持っています。
勉強の基礎にはこだわる
次に、「勉強の基礎にはこだわること」です。
勉強は楽しくできればいいですが、やはり結果も伴っていないと、楽しさは持続しません。努力や苦労をした結果、成功体験をすることはとても重要です。
成功体験はどんなものでもいいですが、特に漢字、計算、地図や年号などの暗記が目に見えてわかります。そして、小学校まではこれらは勉強の基礎になります。
基礎がしっかりしていれば、発展問題も解くことができ、さらに成功体験をさせることができます。
ゲーム化する
次に、「ゲーム化すること」です。
勉強には反復練習が大事で、勉強好きな子どものママ、パパは子どもに反復練習をさせることが上手です。その1つがゲーム化です。
例えば、百ます計算をストップウォッチでタイムアタックしてみたり、ママ、パパとどちらが早く解けるか競争してみたり、楽しめる工夫をしています。
努力は大事ですが、すべてを努力で解決するのは、難しいことです。できるだけ苦労しないですむのであれば、しないほうが、子どもも勉強が好きになるはずです。
やる気があっても、やらせすぎない
そして、「やる気があっても、やらせすぎないこと」です。
勉強好きな子どものママ、パパは、勉強をやらせすぎることはしません。勉強をまだやりたいと思うタイミングで、勉強をストップさせます。
中途半端に終わることで、やりたい気持ちが持続することって、勉強以外でもありますよね。達成感を感じすぎる前に終わらせることで、明日勉強するやる気をとっておくのです。そのおかげで、勉強へのやる気を毎日持続させることができます。

まとめ
いかがだったでしょうか。勉強好きな子どものママ、パパの関わり方をお伝えしてきました。
子どもを勉強好きにするには、勉強に対しポジティヴなイメージがつくようにすることが効果的なようです。ぜひこれらのことを参考に、子どもを勉強好きにして、やる気を引き出してみてください。